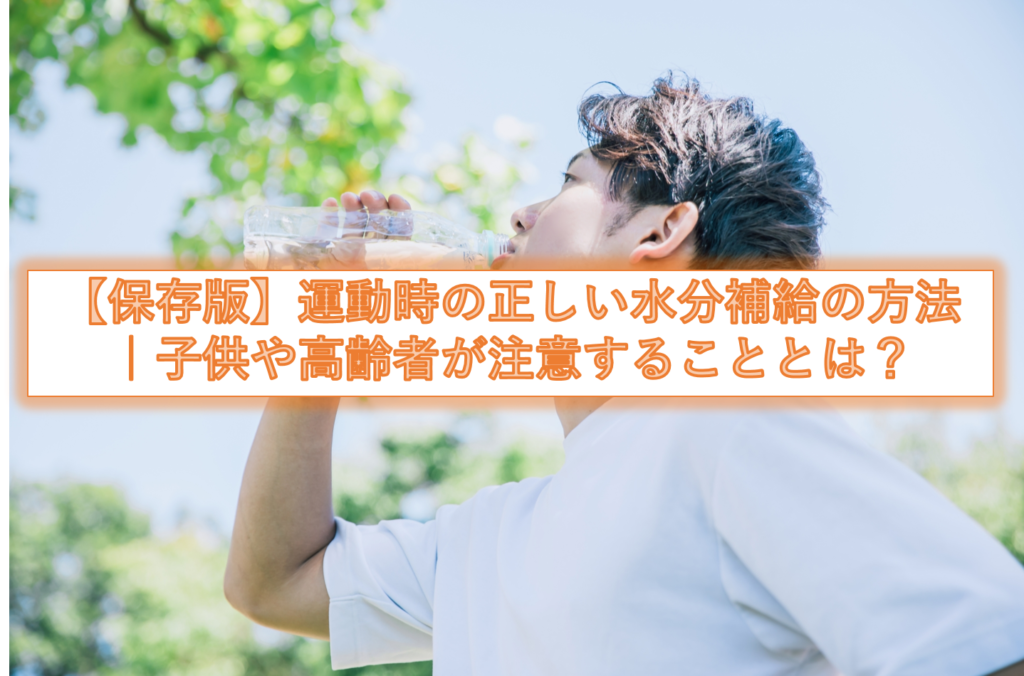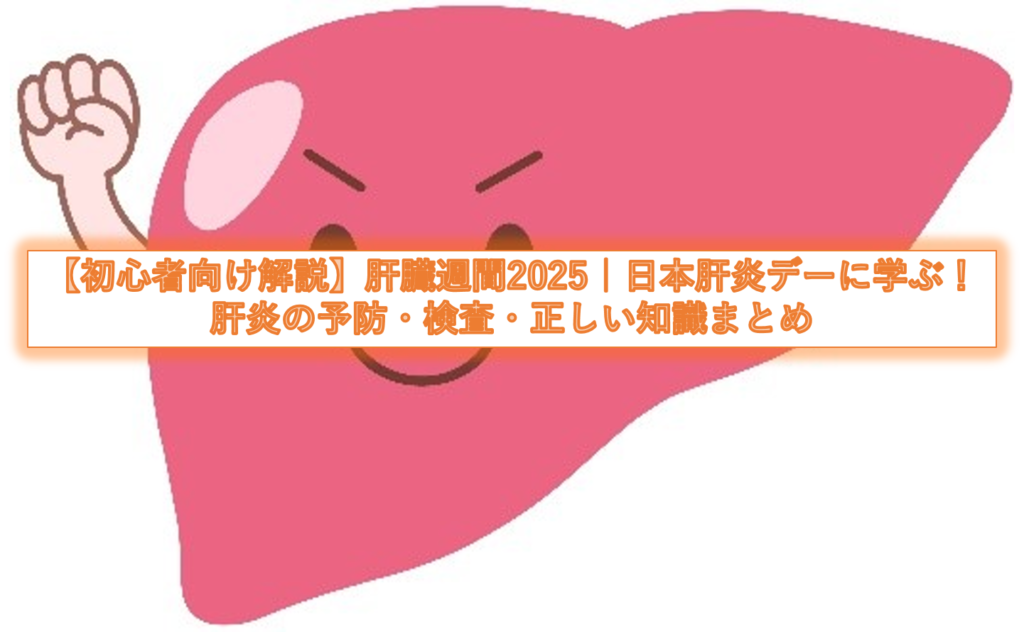心不全予防は家族の支えから!日常でできる予防方法とは!?
目次
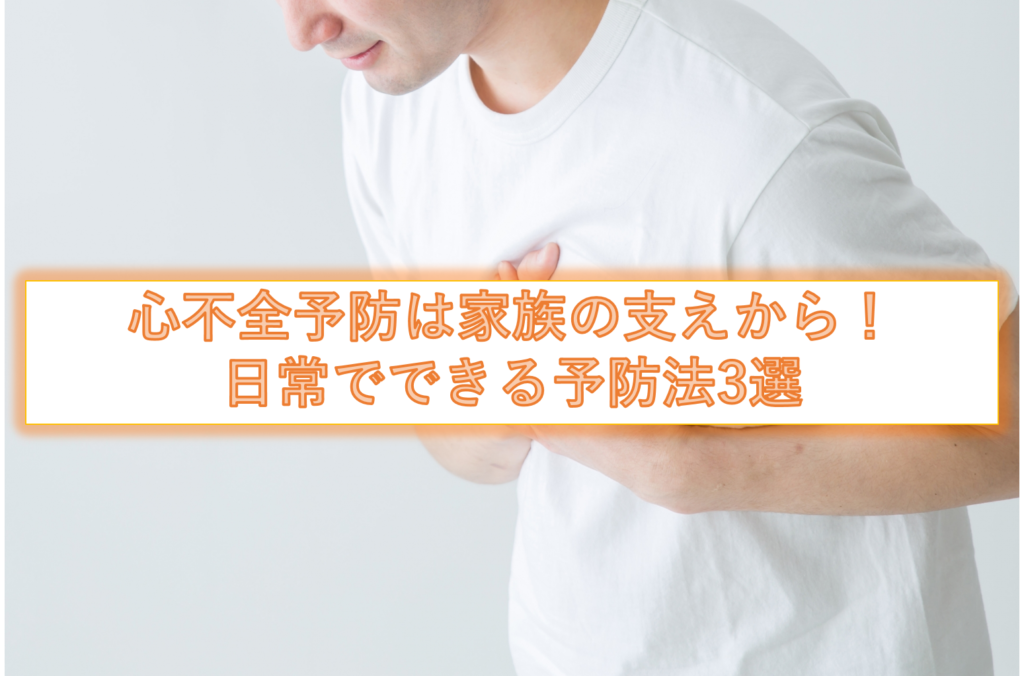
こんにちは。スリーウエルネスの理学療法士の原田です。
少しずつ暖かい日があったり、また寒くなったり、季節の変化を感じるようになりました。気温の変化で体調を崩してしまっている方もいるのではないでしょうか?季節の変化に伴い、疲れやすかったり、むくみやすかったりしていませんか?そのむくみ、放っておいて大丈夫ですか?大切な人の変化に気付けるよう、知識をつけませんか?そんな方はぜひブログを読んでみてください!
今回は、体調不良の裏に潜む、心不全のお話をしようと思います。
心不全とは?
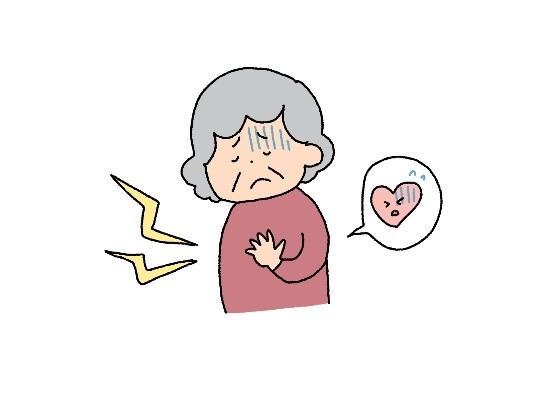
日本循環器学会と日本心不全学会は【心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気】と一般向けの定義を公表しています。
我が国の循環器疾患の死亡数は、癌に次いで第2位となっており、心不全による5年生存率は50%と予後についても決してよくありません。ただ、その事実と心不全の怖さについて、国民にあまり知られていないのが現状です。このため、心不全について、国民により、分かりやすく理解してもらうため、新たに「心不全の定義」を作成したそうです。
心不全はなぜ起こるのでしょうか?死因ともなる「心不全」ですが、病気の名前ではありません。心臓は収縮と拡張を繰り返し、ポンピングしながら全身に血液を送っています。心臓に何等かの異常があり、心臓のポンプ機能が低下してしまい、全身の臓器が必要とする血液を十分に送りだせなくなった状態をいいます。十分な酸素がいきわたらないので、各臓器の機能が低下してしまいます。この状態がさらに進行すると、死に至ります。
心不全の原因

実は、心不全の原因は、様々あります。
心筋の異常による心不全
虚血性心疾患、心筋症など
血行動態の異常による心不全
高血圧、弁膜症、心臓の構造異常など
不整脈による心不全
頻脈性(心房細動、心房頻拍、心室頻拍など)、徐脈性(洞不全症候群、心房ブロックなど)
上記以外にも全身性の内分泌・代謝疾患、炎症性疾患が原因となったり、栄養障害や薬剤、化学物質といった、外的因子による心筋障害から発症することもあり、心不全の原因が心臓以外に存在する場合もあるのです。
心不全の症状
心臓の働きが悪くなりはじめた段階では代償機構が働き、自覚症状をほとんど感じません。息切れがするな、疲れやすいなと思っていても、年のせいかな?と放っておくことは危険です。心不全は十分な血液を送りだせない、「ポンプ機能の低下」によっておこる症状と、全身から心臓に戻る機能が弱くなって「血液のうっ滞」によっておこる症状があります。

ポンプ機機能低下
疲労感が強い
運動後の回復に時間がかかる
手足が冷える
睡眠中の息苦しさで目が覚める(発作性や感呼吸困難)

血液のうっ滞
身体を動かした時の息切れが強い
持久力の低下
足のむくみ
上記のように、日常生活でも感じやすい症状なので、心不全と症状を結びつけるのは難しいのです。異常な疲労やむくみ、息切れを感じたら、医療機関を受診するのが一番です。
心不全の予防方法
心疾患の予防には運動も重要ですが、薬や食事も重要です。どれか一つだけでは効果が少ないため、バランスよく取り組みましょう。
運動
運動に慣れていない方は5分~10分程度のストレッチから始めるのも良いでしょう。有酸素運動の目安として、20分~30分程度で息が弾むくらいを目安にしてみてください。有酸素運動はエアロバイクやウォーキング、体操やエアロビクスなど楽しく続けられるものを選びましょう。
食事
脂質や塩分、当分、水分の管理も必要です。脂身の多い肉は避け、塩分は6g未満で調整します。心不全の方は水分の取りすぎにも注意が必要です。
服薬
血圧を下げる薬や血管を広げる薬、尿を出す薬など、医師や薬剤師の指示通り、正しく飲みましょう。
心不全のご家族がいる方へ
高齢化社会に伴い、介護予防は大きなテーマですが、心不全の再発でも要介護状態になることがあります。今後我が国では後期高齢者の心不全発症率が爆発的に高まる、心不全パンデミックに対する対策が必要です。家族介護で有効な心不全の症状のチェック方法について紹介します。
在宅介護する中で、心不全が悪化する要因を抑えていることは重要です。そこで、気を付けておきたい、生活習慣とその対策についてご紹介します。
水・塩分の取りすぎ
水分・塩分の過剰摂取によって、血管内の水分が多くなると、心臓の負担が大きくなります。病院では水分制限や減塩食などの対応で心不全の悪化を防いでいますが、退院前に指導されたことを自宅でも続けることが重要です。
高血圧や心不全がある方の場合、塩分は1日約6グラムに制限されることが多いですが、自宅で毎食計測することは難しいでしょう。減塩醤油を使ったり、一口ごとに少量の醤油をつけて食べるなどの工夫も効果的です。退院前に病院の管理栄養士に質問したり、退院後であれば市販の減塩レシピを活用していきましょう。
薬の飲み忘れ
循環器疾患では処方される薬の量が多いですが、飲み忘れがないよう注意が必要です。町の薬局では朝・昼・夕用にそれぞれのポケットのついたカレンダーが販売されていたり、百円均一でも薬の管理がしやすいピルケースなども販売しているので、活用してみるのもいかもしれません。
誤嚥性肺炎には注意
肺炎や風邪などで体の熱が上がると心臓への負担も大きくなるため、それを契機に心不全が悪化することがあります。また、肺炎の中でも、誤嚥性肺炎と呼ばれる肺炎は水分や食事が気管に入ることによって発症することが特徴です。普段の食事の場面は水分にとろみをつける、一口大にカットして配膳するなどの工夫が有効です。
ここで紹介した3つのポイントは普段の生活の中で家族が対応しやすい項目を挙げていますが、必ず心不全が予防できるわけではありません。体調の変化にいち早く気付くことは早期治療による入院期間の短縮や再入院の回避につながります。
次は家族ができる心不全悪化の兆候について解説します。
心不全悪化の兆候とは

チェックポイントは、首、胸、足
◎首:血管をチェック
◎胸:息切れしていないかチェック
◎足:すねや足の甲が浮腫んでいないかチェック
「首・胸・足」のチェック方法をご紹介
◎「首」は血管が浮き出ているかを見る
心臓から血液を送り出せなくなると、その少し上の上流にある、首の静脈系に負担がかかってきます。すると、溜まった血液によって首の血管が太く浮き出て見えることがあり、専門用語ではこれを「経静脈怒張(けいどうみゃくどちょう)」と呼びます。
寝ている時は首と心臓はほぼ同じ高さにあるため、見えやすいですが、座っている時にこの症状が観察される時は要注意です。
◎「胸」は寝ている時や軽い動作で息切れがあるかを見る
医療スタッフは聴診で胸の状態を確認しますが、聴診をしなくても、水が溜まっているかを推測することができます。「寝ていると苦しいけど、身体を起こすと楽になる」という訴えがある場合や、トイレに移動するだけでも息切れがある場合は要注意です。前者は起座呼吸(きざこきゅう)と呼ばれる症状で、寝ている状態では心臓に戻る血液の量が多くなるため、座ることで症状が軽快することが特徴です。
◎「足」はすねや足の甲がむくんでいるかを見る 心不全で足が「むくむ」ことをご存知のご家族も多いかもしれません。チェックする際に靴下の後がいつもより深く残るかどうかです。これは専門用語で下腿浮腫(かたいふしゅ)と呼ばれるもので、心不全の代表的な兆候です。
「首・胸・足」をチェックする理由
心不全では高血圧や水分過多などの理由で心臓から血液をスムーズに送り出すことが困難になります。しかし、全身を巡った血液は心臓に帰ってくるため、心臓の上流にあたる肺や静脈系に血液がうっ滞します。
静脈系(心臓に血液を戻す血管)は動脈系(心臓から血液を送る血管)と比べて血管の壁が薄く、血液がたまって、パンパンになると周囲に水分が溢れます。 この時、外見から分かりやすい場所が「首・胸・足」であり、これらの場所に水分が溜まっていると、心不全が悪化していると解釈できます。
いつもでも住み慣れた家で生活するために家族ができること

心不全の再発によって、入退院を繰り返すと、徐々に身体機能が低下して家族の介護負担も増える可能性があります。心不全は急性心筋梗塞や不整脈など循環器の病気だけではなく、日々の生活の中でも悪化する病気です。しかし、悪化の兆候をいち早く察知し、速い段階でかかりつけ医に相談することができれば、入院を回避できるかもしれません。
大切な人がいつまでも元気でいられるように、また、住み慣れた家で安心して暮らせるためにも知っておいて欲しいです。
スリーウエルネスでできること

スリーウエルネスのパーソナルトレーニングは、理学療法士などが在籍しているので、健常者だけでなく、疾患をお持ちの方なども、楽しく、安全に運動が出来る体制を整えています。1人でジムに行くには不安な方、何から取り組めばいいかわからない方などは、体験トレーニングもございますので、一度、スリーウエルネスへお問い合わせください。

参考・引用